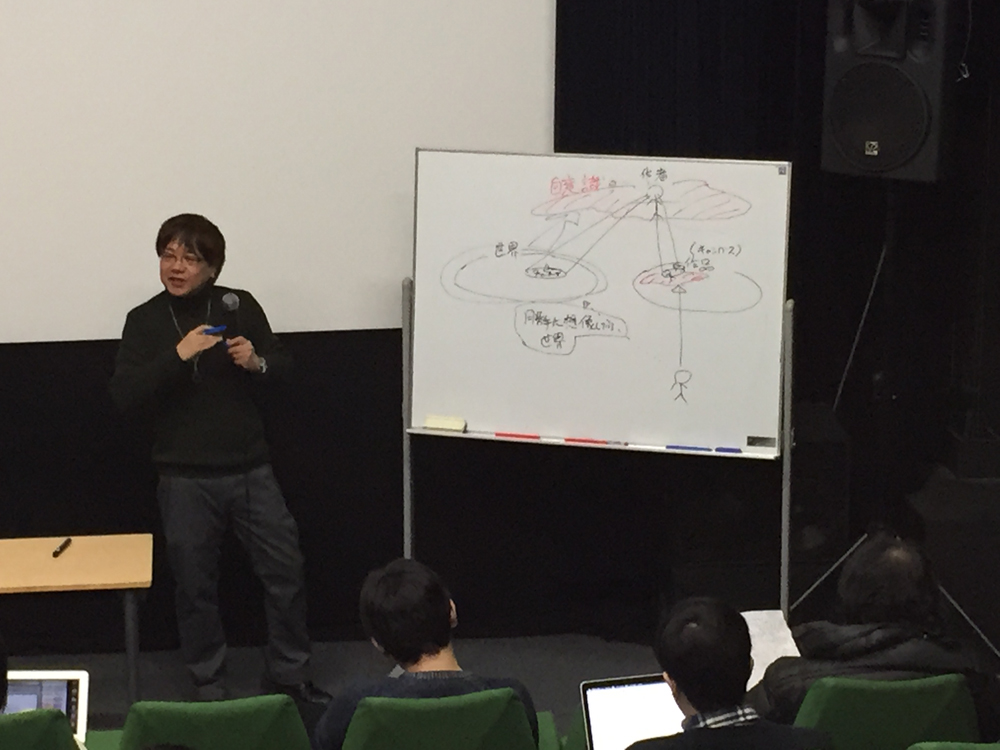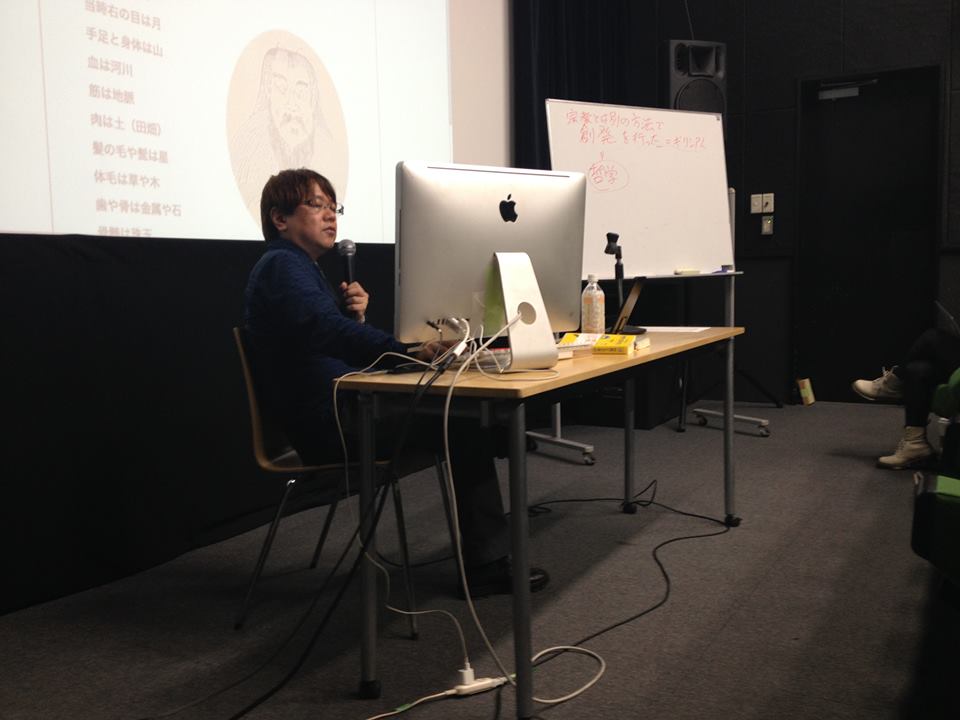「メタフィクションの教室」を終えて(村井さだゆき)
映画美学校で講師をするようになって良かったことの一つは、あるテーマについて教えようとすることで、自分でも改めてそのことについて考え直し、時に新たな発見があることだ。
3月17日~25日までの間、全5回の特別講義として「メタフィクションの教室」というのをやらせて貰った。最初は創作についての入門的な話をという打診があって、軽い気持ちで引き受けたのだが、お題を「メタ~」にした段階で、えらく大変な──面倒くさい話にならざるを得なかった。
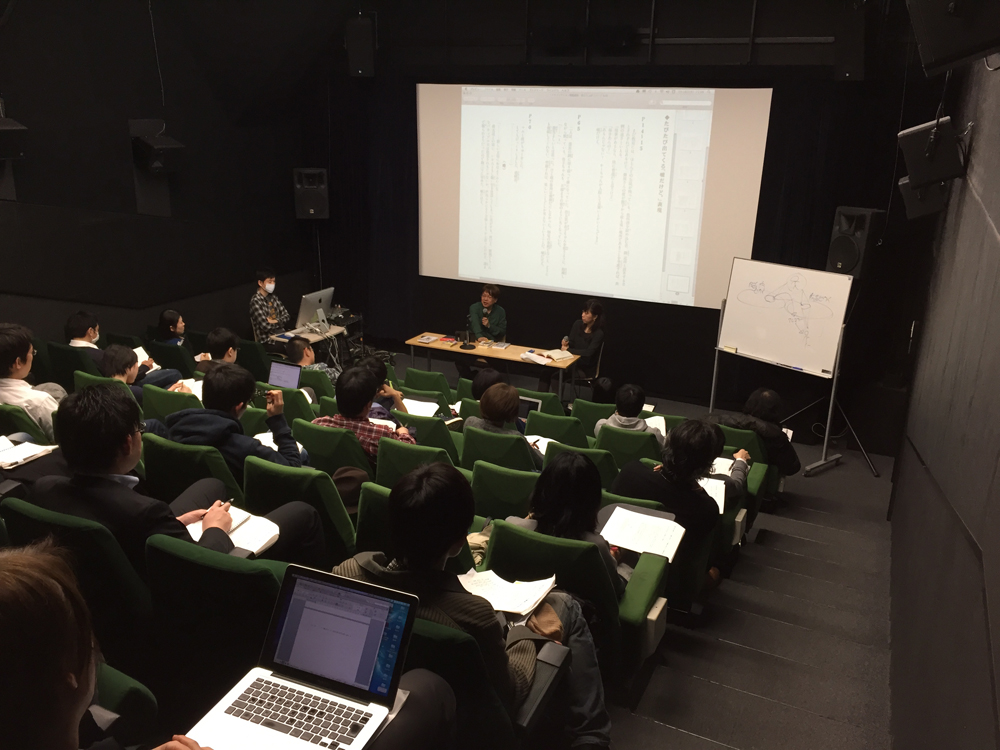 そもそも、僕ら作り手が自分から「メタフィクション」への興味を明かしてしまうのは、まさに語るに落ちるというか、手品の種を明かすような真似をやって得することは何もない。
そもそも、僕ら作り手が自分から「メタフィクション」への興味を明かしてしまうのは、まさに語るに落ちるというか、手品の種を明かすような真似をやって得することは何もない。
それでもこのお題を選んだのは、日々の創作に追われる中でちょっと立ち止まって、今一度このテーマをじっくり考え、自分の中で総括しておきたいと思ったからだ。
結果としてやって良かったと思う。ただ、毎回大雑把に話の構成は考えていくものの、3割くらいはその場の思い付きで話すので、ずいぶんとっちらかって受講者には迷惑をかけただろう。その中でこぼれ落ちてしまった話や、上手く説明できなかった部分、さらに新たに出て来た疑問やテーマがいくつかあるので、ここに順不同で列記しておく。
・「洞窟の中の思考」について
「メタフィクションの教室」では、第1回の講義をアルタミラ洞窟壁画発見の逸話から始めた。これは「物語の歴史は洞窟の中で始まった」という言い方が、フィクションの講義を始める上で、僕の中でしっくり来たからだったが、話がプラトンのイデア論に及んだ時に、この二つは奇妙に響きあっている、ということを話すべきだった。講義の組み立てを考えた時にぼんやりと、ああこれはプラトンの「洞窟の比喩」を絡めて話せるかもという予感はあったのだが、うっかり話しそびれたのだ。
「洞窟の比喩」は、我々人間はモノの実体を直接見ているのではなく、モノ自体が外の光を浴びて洞窟の壁に映っている影を見ているのだ、というイデア論の説明だ。アルタミラやラスコーの壁画をこの影に喩えれば、その意味がもっと解りやすかったはずだ。さらには、カントの「物自体には触れられない」という考えとイデア論が、一見真逆のようで似ている、という話も理解がしやすかったろう。
もっというと、〈セカイ系〉の「キミとボク」の自閉したセカイも、この洞窟に喩えられた。キミとボクに対して外部は壁に映る影として襲い掛かってくる(アゴタ・クリストフの戯曲「怪物」を想起されたし)。こういう自閉を非難するのは簡単だが、洞窟のセカイを捨てて外に出たと思っても、そこもまたもう一つ上の次元の洞窟の中なのだ、というのがメタフィクション的な一つの回答だ。
第5回だったと思うが、受講者の一人に「この議論は「神」と関係があるのか」というような質問を受けた(うろ覚えでごめんなさい)。その時僕はピンと来なかったので曖昧な答えを返してしまったが、あとあと考え直して、はたと気が付いた。この種の議論は、いつも一種の神学と深く結びついていたではないかと。
「メタフィクション」では、世界を俯瞰する位置に立つ必要があるが、前述のようにその位置もまたたちまち世界に含まれて、俯瞰と世界の追いかけっこが無限に続く。この無限というのが、神の存在と関わってくる……というのも、デカルトによると神は無限だからだ。
僕がよく話に出すアリストテレスも実は神の存在証明を行っている。世界はいったん動き始めればその後は自動的に動くことが可能だが、最初に神の一撃が要ったはずだ、というのである。これはそのまま、世界を物語と言い換えてもいい。
質問者の頭にはこうした西洋哲学的な神論があったのかも知れない(あるいは講義を聞いている中で自力でそこに辿り着いたのかも)。どうも僕はアニミズム的な素朴な神様感覚にどっぷり浸って育ったせいか、こういった神の概念には勘が働かない。しかし、神をアプリオリ(先験的=人間の経験に先立って)に実在するもの、と言い換えると、なるほど何か関係があるような気がしてくる。うーん、まだよく解っていないが……。質問してくれた人にはピント外れな答えをしてしまって申し訳なかった。
 ・カントールの無限と不確定性原理の不思議な響きあい
・カントールの無限と不確定性原理の不思議な響きあい
第4回の講義でパラドクスを扱った時、「集合論」によって数学が論理学と一体となった、という話はもっと解りやすく説明できるはずだった。話は簡単で、
(1)数学は集合論によって記述し直せる。
(2)集合論は論理学である。
(3)ゆえに数学は論理学である。
という三段論法で話せばいいのに、順番を間違えてカントールの対角線論法から話し始めたもんだから、すっかりグダグダになってしまった。
いずれにしても専門家ではない我々は感覚的な理解で良いのだから、ここで厳密に証明する必要はない。(2)について、集合論が何となく論理学と似ている、ということは感じとして分かるだろう。パソコンにはディレクトリという階層概念がある。パソコン内の世界はすべてがディレクトリという集合とその要素として理解できる。言葉が世界を分節化する仕組みにも階層化の原理が働いている。動物∋哺乳類∋ヒト、というように。これも集合だ。こういった世界の様相を論理記号で表現していけば即ち集合論になるというのは、比較的納得しやすい。(2)についてはその程度の理解で良かった。
あとは(1)について、そーなんだ、と乱暴に言い切ってしまえば良かった。興味のある人は自力で調べて欲しい。
そしてそこからすぐにラッセルのパラドクスに持って行けば、対角線論法の説明は必要なかったのだ。しかし、自分の手に余ると思いながら無理やりこの対角線上の悪魔について解説を試みたことは、自分の中で予想外のアイデアを生むこととなった。
第5回の講義の終わりのほうで、ハイゼンベルクの不確定性原理はゲーデルの不完全性定理とジャンルは違えど似た感じがするという話をしたが、そこでふと思いついて、量子力学の世界における粒と波の特性を、カントールの無限集合論における自然数と実数に喩えてみたのだ。すると妙にしっくり来る。どういうことかというと、だいたいにおいてこの世界は粒の理屈と波の性質で理解できるのではないか、と僕は思っている(元ネタは「思考の道具箱」ルーディ・ラッカー著 工作舎)。粒はデジタル、波はアナログ──数学に当てはめると、デジタルは自然数、アナログは実数だ。しかし、量子力学では、粒の理屈は誰かが観測して初めて現れる。この理屈が数直線上の自然数と実数にも当てはまると仮定すると、人が数えることで初めて自然数が立ち現れると言っているのと同じじゃないか。
ならば、人が存在せず、誰も数を数えないと自然数は実在しないのだ、と考えることも可能なのか。ゲーデルが強力な実在論者だったことはよく知られるが、彼やプラトンは間違っていたのか。いやしかし、それでも自然数は先験的に実在するように思われる……。こっから先はもはや僕の手には負えない。
ただ、不確定性原理が似ているのは不完全性定理ではなく、むしろカントールの無限論のほうかも知れないというアイデアは、何か本質を突いたような感触が自分の中で残っている。
・「キャラクターがシチュエーションとは別の仕方で物語を駆動させる」こと
物語が発動する瞬間のことを、ラスコー洞窟の二枚の壁画、人が倒れている場面(シチュエーション)と、一角獣(キャラクター)を使って説明したのだが、キャラクターがシチュエーションとは別の仕方で物語を駆動させるという言い方は、ほぼその場の思い付きだった。
自分で言ってみて、これは本質を突いた気がする。ただ、キャラクターが物語を駆動させる理屈が解らない。ここでいうキャラクターとは、何らかの特異なコードを背負った人物という作劇上の性格ではなく、ゆるキャラとかご当地キャラとかそーいう……物神性を持ったキャラと言ってもいいかも知れない(講義では混同して話してしまったが)。
シチュエーションが物語を動かす理屈は比較的理解しやすい。緊張の種が次の行動を誘発するのだ。しかし、キャラクターが、シチュエーションとは無関係に物語を誘発するのはどういう仕組みだろう。
僕はまだ上手い説明を思いつかないが、皆さんも考えてみて欲しい。
当たり前といえば当たり前だが、ものすごく大事なことのように思われる。だが一方で我々は荒唐無稽な物語も受け入れることが出来る。講義ではこのことを、フィクションライン(三宅隆太さんの言葉)と、マチエルを揃えるという僕の言い方で説明を試みたが、まだ不十分な印象だ。
フィクションの作り手にとって作品にリアリティが必要なことは自明だから、我々はどうすればリアリティが出るかを考えれば良いのだが、僕は何故フィクションがリアルの真似をしようとするのかを考えたい。あるいは逆に、どんな場合に受け手(読者・観客)の側に「不信の停止」が起こって、リアルではない荒唐無稽な表現が成立するのか。そこには人間の「認識」の仕方に関わる本質が隠されている気がする。
・メタ的実感について
結局、今回の特別講義はその7割くらいがメタフィクションではなく、フィクションの本質の話に終始した。その中で、作者が実感していることを他の誰かにも実感させたい、というのが創作の動機だという話が出て来た。さて、メタフィクションでは作者が世界を俯瞰する位置に立つ。その立ち位置もたちまち上の次元の世界に包摂される。洞窟を飛び出しても飛び出してもどこまで行っても洞窟の中。この迷宮の中で立ち尽くしてしまう自分の実感。これをメタ的実感と呼ぶならば、それもまた受け手に伝えたいという欲求が生まれるだろう。
この実感はいくら口で説明しても伝わらない。だからメタフィクションはフィクションの形態をとらなければならないのだろう。これが全5回の講義の結論の一つだ。
結局我々はどこまで行っても洞窟の中で夢想を広げているだけなのかも知れない。でも、「洞窟の中の思索」も案外楽しいものだと、引きこもり体質の僕は思う。
(了)
村井さだゆきさんが担当される脚本コース第5期初等科概要はこちらから