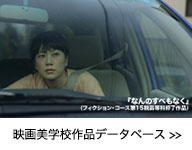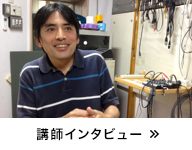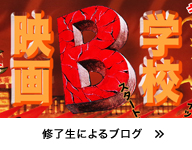「プロット・コンペティション2025」 選考結果発表!
2025年2月18日締切の「プロット・コンペティション2025」の応募総数は25本でした。各選考者による選考結果・選評は以下となります。
<プロット・コンペティション2025 選考結果(選考者五十音順)>
【江守徹プロデューサー選出】
根岸摩耶『狭いながらも』(脚本コース第9期高等科後期修了)
【鈴木徳至プロデューサー選出】
選出作品なし(佳作あり。佳作は選評に記載)
【山田真史プロデューサー選出】
選出作品なし(佳作あり。佳作は選評に記載)
【西川朝子プロデューサー選出】
選出作品なし(佳作あり。佳作は選評に記載)
ただし、すぐに実現可能なものではない、という条件付きでの選出です。作品の作者は、これから選出プロデューサーと顔合わせを行い、具体化を目指して話を進めていきます。
各選考者による選評・総評
【江守徹(IKエンタテインメント・プロデューサー)】
【選出作品】
『狭いながらも』 根岸摩耶さん
【選出理由】
久し振りに選考者を拝命させて頂きました。
相変わらず選考作業はとてつもない疲労と緊張に襲われます。
応募者の方々の人生模様や心情が濃密に迫ってくるのを受け止め、評するのはとても苦しくて幸福な時間でした。
選出した根岸さんの『狭いながらも』。
ヤングケアラー、投資詐欺、貧困、格差、家族、血・・・様々な要素をてんこもりし過ぎた感もあり、希薄で脆弱になりがちなところをギリギリ踏み留まって、1本の映画脚本として立脚している。
なによりも文章から人がもがきながら生きる躍動を真摯に感じれた。
まだまだ本当に粗削りなホンですが、以前選出した弥重さんに負けない光と才能を感じ、思い切って選出しました。
【総評】
各々の技術やスキルは向上しているのですが、今回は全体的に小さな世界を丁寧に描いたものが多いように感じます。
映画の世界はとても広いので、予算勘案も大事ですが、拡がりのある物語も期待したい。
さて、選にはもれたが、確かな力量と可能性を感じたものを佳作として挙げます。
●宇佐美友紀 『ビヨンド丁寧な暮らし』
●太田慶 『愚者の惑星』
●加藤高浩 『嘘つきたちの愛』
●神田星平 『しぬよろこび』
●小滝薪 『ウリハンブリ』
●野原由香利 『Nobody was』
●村田玲央 『漫画を描かない私たち』
最後に前回も同様に書きましたが、本企画は今後の映画映像業界にとって大変意義深く重要な取り組みだと思います。
継続的にこの新たな才能に光を当てる動きが続くことを改めて願います。
【鈴木徳至(コギトワークス プロデューサー)】
今回初めて審査員という役割を拝命し、25本の刺激的なプロットと向き合う中で、自分自身の価値基準の曖昧さや、それを形成してきた人生のいい加減さにまで思い至り頭を抱える日々でしたが、何か重要な気付きを得たような実感もありますので、少しでも共有させて頂ければと思い筆をとっている次第です。
まず自分が「プロデューサーとして着手したい」と感じる企画というのは、「内容が面白い!」「いい映画になる!」という衝動以外に、「予算を集めて利益を生む」という実務的な責任を全うできる見通しがどうしても必要になってきます。ただ斬新で先駆的な作品を好む場合、多くの場合それらは両立し得ないですし、故に実現できずに抱えたままになっている企画がいくつもある、というのが情けないですが自分の現状だったりもします。
脚本家が企画者としてオリジナル作品をプロデューサーに持ち込む場合、同様に「作家性/商業性」両軸でのプレゼンが必要になってくると思いますが、それらをどちらもクリアできていると感じる作品には今回出会うことが出来ず、大変心苦しくはありますが「選出作品なし」とさせて頂きました。
その中でも、可能性を感じた企画やプロットについては下記に挙げさせて頂きます。
▼神田星平さん『しぬよろこび』
「健康な老人が安楽死を求め、全力で努力する」という設定には魅力を感じました。ただブロットが最後までまとまりきっておらず、残念でした。命の尊厳を滑稽に取り扱うという視座には風刺とオリジナリティがあると思いますので、練り上げて頂きたいです。
▼小滝薪さん『우리한풀이 ウリハンプリ』
世間的に知名度の低い政治的な事件の中に普遍性を見出し、青春譚に落とし込んでいくという方向性はとても好きです。企画の軸がしっかりしている分、物語にはもっとエンターテインメントとしての仕掛けがあってもいいのではないかと感じました。特にホラーという要素はもっとクライマックス部分にも活かせるような気がします。シリアスな題材をコメディとして昇華していくことができれば、より強い映画になると思います。
▼船越凡平さん『おやすみ さよなら またあした』
認知症を扱った映画は既に多くの傑作が存在しますが、「主人公の意識に寄り添い、全編若い頃のビジュアルのままで通す」というコンセプトには新しさを感じました。2幕の頭で違和感から入り、状況を理解したのちにしんみりとした感動へ、という観客の感情の流れも明確に想像することができます。ただ後半の展開が感傷的なところにまとまっていってしまうのが少し残念に感じました。土地の設定で歴史やスケール感を描いたり、現実の中に記憶が紛れ込んでしまうマジックリアリズムなど、映画的な表現の余地が沢山ある作品だと思います。
最後に全体の感想として、やはり25本も同時期に着想された作品が集まりますと、設定やモチーフが被ってきてしまうことも多かったです。(例:いじめ、性加害、発達障害、格差、ルッキズムなど)現代社会において重要なテーマほど、多くの方が描きたいと感じるということなのだとは思いますが、被ってしまった場合それをどう料理して独創性を担保していくのか、という部分が大きく評価対象になり得ると感じました。なので書き手は自身の企画の突破力やオリジナリティは何なのかを自覚しておく必要があると思います。そしてその辺りが梗概に簡潔にまとまっていると、読み手に対して親切かもしれません。梗概の内容としては「タイトル/ログライン/あらすじ/ステイトメント(企画意図)/主要登場人物」など、通常企画書に記載する事項が一式揃っていると読み手にとっては大変有難く、その部分をプロットより先に、丁寧に時間をかけて練り込んでいく作業が重要ではないかと思いました。以上、簡単ではございますが総評とさせて頂きます。有意義な企画にお声がけ頂き、ありがとうございました。
【山田真史(コギトワークス プロデューサー)】
審査なんておこがましい身ではありますが、何が映画になって、何が映画にならないのか、何が面白くて面白くないのか、何が売れて売れないのか、を日々考えています。自分がまだまだ駆け出しの身だからこそ応募された皆さまに近い目線で考えられるのではないかと思い、審査に臨みました。
自主映画は、自分一人が面白いと思えば作り始められますが、商業映画の企画が成立するには、何か一つ以上の大きな武器が必要です。その武器を手に各所を説得し仲間になってもらわねばなりません。武器はさまざまですが、監督、俳優、面白い原作など、そういった側面から企画が通る映画が大半だと思います。無名のライターが書いたプロット1本で「これは・・・」と人々に思わせるには、相当飛び抜けたものが必要になります。そういった意味で、選出作品はありませんでした。
もちろん心惹かれたプロットもありましたので挙げさせていただきます。
佐々木ひとみさん「問題のある家族」:
主人公が自分とは価値観の合わない家族の中に入って、本性を暴いていく展開は面白く読みましたが、唐突に終わってしまいました。家族と組んで叔父にギャフンと言わせるなど、ラストにもうひと展開欲しかったです。
船越凡平さん「おやすみ さよなら またあした」:
主人公をどの時代でも統一したビジュアルで表現したいという部分も含め、どのような映画にしたいのかビジョンがはっきりと見えるプロットにまとまっていました。ささやかでかけがえのない映画になると思うのですが、一方で展開や出来事の物足りなさも感じました。
横山裕香さん「(タイトルが見つけられませんでした)」:
幽霊が主人公の物語がゆるく始まったなぁ読み進めていたら、ほろっとさせられました。幽霊のルール(触れる/触れないなど)の整合性が気になります。また、主人公の死因、家族と祖母との関係がもっとストーリーに絡むと良くなるのではないでしょうか。
以上のプロットは、作者がなんとなく思いながらも言葉にできないような”今”の空気感をセンスと努力でなんとか作品に落とし込もうとしていると感じられました。
他に、内音坊夏奈さん「さらば」、宇佐美友紀さん「ビヨンド丁寧な暮らし」、神田星平さん「しぬよろこび」、ミラーレイチェル智恵さん「(タイトルが見つけられませんでした)」は、テーマの面白さを感じましたが、もっと練ってもらいたかったです。
最後に、”自戒も込めて”全てのプロットを読んだ全体の印象として、
・もっとタイトルを練って、主張してほしい
タイトルは作品の顔です。コンペだとタイトルが印象に残らないと、記憶にも残りません。自分の名前と同じように表紙に大きく書いてもらいたいです。
・誤字だけでなく読みにくい文章が多く感じました
提出前に人に読んでもらっているでしょうか? やっとつかんだチャンスで有名プロデューサーや監督に会ってプロットを渡すとなったら、本当にこのままで渡すでしょうか? 文字を扱う仕事なので、日頃から大切にしていただきたいです。
以上です。知ったような物言いで、すみません。皆さまに負けずに精進します。
熱いプロット、ありがとうございました。お疲れ様でした。
【西川朝子(株式会社ブリッジヘッド プロデューサー)】
応募された皆さん、プロット作成おつかれさまでした。忙しい日々の中でこうしたコンペに挑戦することは簡単なことではないと思います。ほんとうにご苦労様でした。
審査においては、この作品を映画として観てみたいか。映画の企画として商業性と芸術性を感じられるか。という2つの点を重視しました。その基準に照らし合わせて、
興味・関心の方向に共感するものもありましたが、今回は残念ながらプロデューサーとしてともに開発してみたいと思える企画は見つかりませんでした。
しかし、いくつかの作品ではしっかりとしたリサーチの元、自身の関心事に根拠を以てプロットを作成していることから、物語の背景と人物の動きに説得力が感じられる作品がありました。
〇小滝 薪さん:『우리한풀이 ウリハンプリ』
〇船越凡平さん「おやすみ さよなら またあした」
上記2作品には、書き手の強い意志を感じることができました。「ウリハンブリ」においては、キャラクターの人物造形をもうひと練りしてゆくこと、物語をどのように展開させてゆくかという点をもう少し慎重に検討してみると、グッと魅力が出てくるのではないかと思いました。「おやすみ さよなら またあした」では、もう一息、孫自身の背景、祖母と娘が没交渉になる理由、あるいは祖母と孫の直接的な人間関係の積み重ねがないと、長編としては作り上げられないのではないかと思いますが、物語の始まりや着眼点には興味が湧きました。
もう1本、
〇美野大輔さん「子連れ刑事(デカ)」
については、25本中唯一のサスペンス作品でしたが、上手に作られているとおもいました。が、もし作られるとしてもリアリティラインというか、物語の解像度が甘く、「あり得そう」というサスペンスにはなっていないという点が残念でした。もう一歩丁寧に鋭く設定を詰めていくことができるならば、事件側を観ることで楽しむことはできそうです。ただ、キャラクターはやはり漫画的にならざるを得ない(幼児を抱いて現場に出ることは実際は考えにくい)という点は、テレビドラマ的であると思いました。
最後に、比較的若年層(30歳未満の方々)においては、小説やエッセイなど、人の書いた文章を多く読むことをお勧めしたいと思います。自身の感覚だけで文章を作るのではなく、、今後間違いなく、どんな年齢のどんな背景を持った人にも等しく伝わるような文章を書くことが求められてくるので、まずそうした文章に触れ、真似てみてください。自分の持つ大切な視点を共有するために必要なスキルなので、がんばって読んでみてください。
以上になります。
ご応募頂いた皆さまの今後に期待しております!
お問い合わせ
映画美学校
〒150-0044 東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS B1F
電話番号:03-5459-1850 FAX番号:03-3464-5507
受付時間(月ー土) 12:00-20:00
ウェブサイトからのお問い合わせはこちら